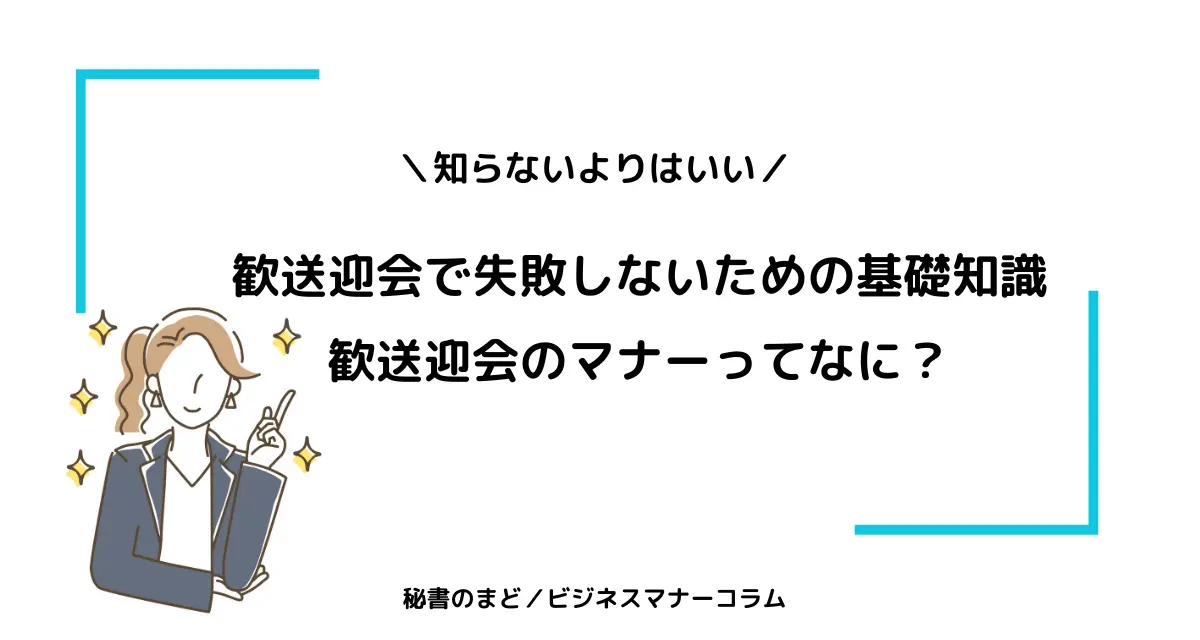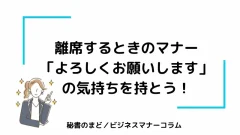新年度や年度末となると、歓送迎会が多くなってきますよね
歓送迎会は、会社によってガチガチに硬いビジネスマナーが求められたり、本当にゆる~いビジネスマナーが求められている場合があり、社風を色濃く表していると私は感じます。
企業ごとに求められるビジネスマナーを網羅することは不可能ですが、最低限知っておきたい歓送迎会のマナーを今回はご紹介します!
歓送迎会のビジネスマナー
歓送迎会は「職場の食事会」ではありません。主賓(しゅひん)である退職者を歓送(かんそう)したり、新入社員や異動してきた配属者を歓迎する、一種のセレモニーです。

歓送迎会は、決して退職者や新入職員でもない社員が飲んで騒ぐような場であってはなりません。打ち上げの飲み会とは別モノです。

ある程度のマナーがあって、退職者や新入社員が気持ちよくいられる空間を作り出すことが、送る側であり迎える側である私達の使命なのです!
歓送迎会で失敗しないビジネスマナー
歓送迎会で失敗しないビジネスマナーとしてはじめに紹介したいのが次の2点です。
- 出欠の速やかな回答
- 幹事の担当確認
招待を受けたら早めに出欠を伝えましょう。特に欠席する場合は、理由を簡潔に伝えると印象が良くなります。
参加する場合は、幹事が誰なのかを確認します。もしも同じ部署の人なら「なにか手伝うことはありますか?」と声をかけるのがマナーです。

直属の上司が幹事をしている場合は、聞くまでもなく手伝いをします。
たまに上司一人が忙しく動き回って、部下が飲んで騒いでいる状況を見ることがあります。マナー以前に、あまりにも心無いと感じます。
歓送迎会の席次は?
会議室や車、エレベーターに「上座(かみざ)」「下座(しもざ)」があるように、歓送迎会でも席次は重要です。
マナーとしてだけでなく、心遣いと、歓送迎会運営の導線を考えておくことがポイントになります。
- 上座と下座の理解
- 上座: 一般的に会場の出入り口から最も遠い席や、窓側・壁側など「落ち着ける場所」が上座とされます。
- 下座: 出入り口に近い席や、通路側が下座になります。幹事や会計担当は下座につくのがマナーであるだけでなく、会の運営をスムーズにできるため、他の人がなんと言おうと、ここは譲ってはいけません!
- 主賓を優先
- 主賓や新しく迎えられる方(歓迎される人)は、上座に座るのが基本です。
- 送別会では、退職される方や送られる方が主賓となるため、やはり上座に座っていただきます。
- 上司・目上の方の席
- 主賓の隣に上司や目上の方が座るのが一般的です。これにより主賓への配慮が示されます。
- 幹事や若手社員の位置
- 幹事は会の進行や手配を担当するため、下座に座ることが一般的です。また、若手社員も同様に下座に位置する場合が多いです。

テーブルの配置に応じた席次
- 長テーブル(横並び) 主賓はテーブルの中央や出入り口から遠い位置に座ります。
- 丸テーブル 主賓は出入り口から遠い席、または入り口を背にしない位置に座ります。円卓ではあまり厳格ではありませんが、周りのバランスを考えます。
歓送迎会の席次を考えるポイント
- 席次を考える際には、会場のレイアウトや参加者の関係性を考慮しつつ、誰も不快に感じない配慮が大切です。
- 主賓に対して「歓迎」「感謝」の気持ちが伝わるような配置を優先しましょう。
歓送迎会の服装にもマナーがある?
歓送迎会の服装選びは、会場や職場の雰囲気、参加者の層によって異なりますが、ビジネスの場であることを意識した清潔感と適切さが重要です。以下に具体的なポイントを挙げます。
1. 会場に応じた服装を選ぶ
- カジュアルな居酒屋やレストラン: ビジネスカジュアルな服装が適しています。
- 男性:ジャケットにシャツ、ノーネクタイでもOK。ただしジーンズや派手すぎる柄は避けましょう。
- 女性:ブラウスやスカート、パンツスタイルなど、品のあるカジュアルが好印象です。
- ホテルやフォーマルな会場: よりフォーマルな服装が求められる場合があります。
- 男性:スーツにネクタイが無難です。
- 女性:ワンピースやスーツ、またはエレガントなブラウスとスカートの組み合わせが適切です。
2. 清潔感とサイズ感を重視
- 清潔感のある服装は必須です。シワのない服やきちんと磨かれた靴を用意しましょう。
- サイズが合っていることも大切。オーバーサイズやピッタリ過ぎる服装は避けるのがベターです。
3. 派手さを控えた配慮
- 派手な色や過剰なアクセサリーは避け、落ち着いたトーンを選びましょう。
- 女性の場合、ヒールの高すぎる靴や過剰な露出も控えめに。ビジネスらしい品の良さを意識しましょう。
4. 【重要】職場文化を考慮
- 職場の雰囲気がカジュアル寄りの場合、ややリラックスした服装でも問題ないことがあります。一方で、フォーマルな雰囲気の職場では伝統的なビジネススタイルを守るのが無難です。

歓送迎会では、ビジネスの一環であることを意識しつつ、適切な服装を選ぶことで周囲に好印象を与えられます。服装選びが心配なときは、幹事や同僚に相談しましょう。
歓送迎会の幹事の仕事は?
歓送迎会は職場から移動が必要なため、遅刻や会場迷子といったトラブルが発生しがちです。
幹事一人がすべてを担当すると、会場内外の対応が追いつかなくなります。事前に協力者を見つけて、情報を共有しつつ準備にかかることがポイントです。
1. 幹事の事前準備
- 日程の調整: 参加者が出席しやすい日程を決定し、スケジュールを調整します。
- 会場の予約: 会場を選び、人数や予算に応じて予約を確定します。料理内容や飲み放題プランなども確認。
- 案内の連絡: 全員に日時、場所、会費などを伝え、出欠確認を行います。
日程調整は、主賓である歓送者と歓迎者から始めます。主賓は別の歓送迎会で日程が埋まっている可能性があるためです。
同時に、職場の上司には事前に調整予定の日程を伝えておき、確定次第、上司の日程を押さえておきます。
日程を確定したら、日時が合う会場探しに入れます。主賓と上司の日程調整を確定させることは大変ですが、ここさえ完了すればあとは機械的に進めることができます!
2. 歓送迎会の進行計画
- 席次の決定: 主賓や上司の席を優先し、適切な座席配置を考えます。
- プログラムの作成: 挨拶やスピーチ、乾杯やプレゼント進呈などのタイミングを計画し、参加者へ事前に共有することも重要です。
席次の決定は、飲み会のように「くじ引き」で決めるのはマナー違反です。歓送者のそばには付き合いの長い職場の人物を、歓迎者のそばへは、気さくな人物が座るように配慮し、話題が尽きないようにセッティングしましょう!
3. 歓送迎会当日の業務
- 受付: 参加者を案内し、会費を回収します。必要があればリストを作成すると便利です。
- 進行管理: 計画通りに進むよう、スピーチの開始や乾杯などを調整します。
- トラブル対応: 万が一のトラブルが発生した際には、柔軟に対応する力も必要です。
トラブルは「必ず発生する」と思っておきます。会場のスタッフ、店員さんには歓送迎会であることを伝えておき、花束やプレゼントを隠して置ける場所の相談もしておきます。

泥酔者など体調不良者が出た場合は、お店へすぐに相談します。万が一救急車を要請する必要があれば、お店の人に119番してもらうほうがスムーズです。

4. 歓送迎会終了後のフォローアップ
- お礼の連絡: 主賓や上司、参加者に感謝の気持ちを伝えるメールやメッセージを送ります。
- 費用の精算: 会費と実際の支出を確認し、不足分や余剰金の対応をします。
- 振り返り: 次回のためにフィードバックをまとめると良いでしょう。記録しておくと、次回の参考になります!
特に注意したいのは「費用の精算」です。赤字になったときに幹事が自腹で払ったり、逆に幹事だからといって勝手に自分の会費を無料にしたり、余剰金を自分のタクシー代に使うなど曖昧な支出がないようにしましょう。
赤字の場合は、上司に相談の上で後日参加者から徴収するか、目上の方たちから負担する申し出があれば甘えましょう。できれば追加で徴収とならないように、少しだけ多めに会費を設定しておくことをおすすめします。
歓送迎会のおすすめスピーチは?
歓送迎会のスピーチは、歓送される人と仲の良い人で、いくつかのエピソードを持っている人がベストです。また、歓迎者への言葉も話せるような人へお願いしましょう。

歓送迎会の挨拶は?
歓送迎会のうち、歓送される人については略歴をお話しするのが一般的です。
- 入社年度と最初の配属先
- 各部署の経験年数
- 主な業務内容
- 会社に貢献した業務
- 長年お世話になった謝辞
特に4番は本人が間違いなく頑張ったと感じているであろう業務内容にすること、たくさんあってもなるべく2つ程度にまとめることがベストです。
乾杯の音頭もあるのであまりに長いのは好まれませんが、短すぎるのもよくありません。
スピーチには、笑いを取るようなネタをひとつ仕込んでおいて、緩急をつけると良い感じにまとまります。
最後に、長年お世話になったことにつきお礼を述べるとともに、新しい場所での活躍を祈っていますという締めくくりがおすすめです。
歓送迎会のスピーチを頼む注意点
スピーチは、本人以外にとっては学校の校長先生の長いお話しと変わりありません。「1秒でも早く終わってほしい」、「早く料理に手を付けたい」というのが人情です。
スピーチを依頼するときは、「長くても5分以内に、乾杯の音頭に移りたい」など、明確にタイムスケジュールを伝えて、「時間に余裕がないこと」をアピールしましょう。
これは、依頼のときだけでなく、前日にも伝えるようにします。
また、歓迎者向けのお話しも簡単に触れてもらえるように依頼します。
立場上スピーチを依頼せざるを得ない人と、本当に依頼したい人が違うとき

自他ともに、歓送迎会のスピーチをすべき人が明確な場合は、どんなにスピーチが長くても依頼しなければなりませんよね。
こんなときは、依頼すべき人に先にスピーチしていただき、本当にスピーチしていただきたい人は「古き同僚である〇〇部長からもお言葉を頂戴したいと思います」といったように、2人に頼んでしまいましょう。
2人目の人には、先にスピーチいただいた方より砕けた内容で考えていただいて、会場を楽しませるようにします。
あなたが司会役なら、笑うべきところは大いに笑って、会場のアイスブレイク(緊張を解きほぐす)に貢献しましょう!
歓送迎会の乾杯の音頭(おんど)とは?
スピーチのあとに、宴会の開始を宣言するようなもので、短く、簡潔に一言スピーチして「かんぱーい」の発声をするものです。元気があって、肩書のある人に依頼しましょう。
歓送迎会の締めの挨拶は?
歓送迎会の最後にスピーチしていただくのは、参加者の中で最上位の肩書のある人に依頼します。
挨拶の内容には必ず「長年、お疲れ様でした」という内容が入り、また歓迎者へも「これから組織に貢献して欲しい」と言った内容になりますので、最上位の人でなければならないのです
歓送迎会のプレゼントは?

歓送者へのプレゼントは記念品の意味がありますので、長く使えるものや飾っておけるものがベストです。なお、歓送者が男性だけの場合は、花束は小ぶりにしておくと喜ばれます。
歓送迎会プレゼント│定年退職者向け
筆記用具など、長年使えそうなもので、自分では買わないようなものがおすすめです。あわせて、仲の良い職場なら、寄せ書きや、最後に集合写真を撮って後日送ることも良いでしょう。
逆に、1年も絶たず使わなくなうようなものや、食べてしまうとすぐなくなってしまうような食料品などは、高級であっても避けたほうが無難です。長年飾っておけそうな購入なお酒は良いと思います。

歓送迎会プレゼント│異動者向け
異動が転勤を伴うのであれば、退職者並みのプレゼントを用意しておきましょう。
同じビル内での異動であれば、今後も顔を合わせる機会が多いので、高価なものはかえっていい印象がなくなってしまいます。
誕生日プレゼント程度のもので、お返しの必要がない価格帯のものを用意しましょう。

歓送迎会プレゼント│新人向け
歓迎者へは、基本的に何もプレゼントをする必要はありません。明日から同じ職場で働くわけですから、かえってあちこちにお礼を言いに回らせる事になりかねません。
どうしてもプレゼントが必要な場合は、上司に相談の上、仕事に役立つ専門書をプレゼントするなど、お返しの必要がないものを選びましょう。
歓送迎会の2次会のビジネスマナー

無事に歓送迎会の本番が終了したとしても、退職者などは今後合うことも困難になります。
2次会でのんびり語らいたい人もいるでしょうし、そもそも職場によっては「2次会がない歓送迎会なんてありえない」という風潮があることもしばしば。
幹事の場合は、予約するかしないかは別として、2次会の会場となる店の候補を事前に考えておき、店の住所、電話番号などはスマホに保存しておきましょう。
歓送迎会の2次会メンバーは?
2次会は主賓を含むメンバーで行うのが一般的ですが、主賓も家族がお祝いのために待っている場合もあります。

2次会があったら参加可能か、参加できるなら何時まで可能かを確認しておき、無理に誘ったり、引き止めたりしないように注意が必要です。無理に誘っている人がいたら、やんわりとなだめましょう。
また、新入社員や、子育て世帯、介護世帯は早く帰らねばならない可能性が高いので、強制参加とならないよう、自由な雰囲気で参加者を募りましょう。
歓送迎会の2次会の会費は?
歓送迎会の2次会会費は、1次会の会費とは分けておくことが原則です。2次会にも参加したいのに参加できない人の余剰金まで使うのはマナー違反です。
よほど、1次会の参加者全員が了承してくれるような良い職場出ない限りは、2次会の会費は別にするべきです。
ただし、2次会の主賓分の会費だけは、1次会の余剰金で賄うのは全員の了承を得やすいので良いと考えます。
歓送迎会の2次会の会場選びは?
主賓が参加できるのであれば、それなりに落ち着いたラウンジやバーなどがいいでしょう。
ただ、主賓が豪快なタイプで「1次会だけではお腹が満たされない!」というタイプなら、居酒屋などで砕けた雰囲気にするのも問題ありません。
はじめに戻りますが、歓送迎会は通常の打ち上げとは性質が異なり、歓送迎者が気持ちよく楽しみ、思い出に残る時間を作り出すことがポイントです。
基本的にはカラオケなどは避けるべきですが、主賓が望むなら問題ありません。
まとめ歓送迎会のビジネスマナー│最低限の知識とポイント
歓送迎会は毎年あり、社風やメンバーによってマナーは変わります。
ここまでの解説は歓送迎会に関する基本的なマナーですが、趣旨である…
- 歓送者の楽しい思い出づくり
- 歓迎者のモチベアップ
といった趣旨を十分考えて「マナーありき」「前例踏襲ありき」とならないように注意したいものです。

歓送迎会のマナーは、主賓の思い出を作るための補助でしかありません
ぜひ、思い出深くなるような歓送迎会を企画してください。
本日はここまで、Keiでした!